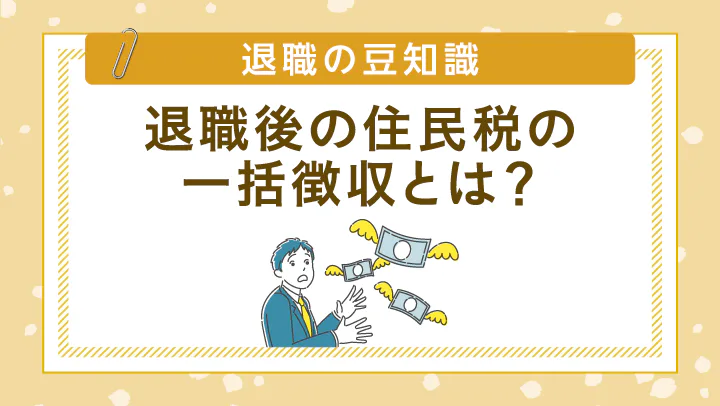
退職時に最終給与から引かれる住民税の「一括徴収」とは?【税理士監修】
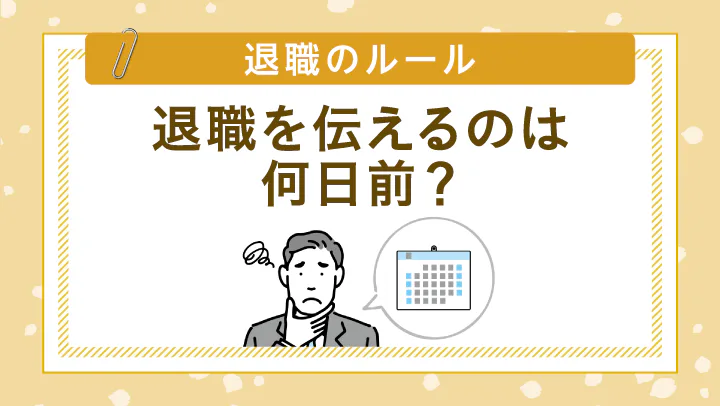
仕事を辞めることは労働者の自由ですが、何も告げずに、とつぜん会社に行かなくなるのはルール違反です。
では、いつ退職することを伝えればよいのでしょうか?
この記事では、退職することを何日前に伝えればよいのか、また、退職の一般的な流れや、円満に退職するためのポイントなどを紹介します。
退職を決めたからといって、何も伝えずに、会社に行かなくなるようなことはNG。
まずは、退職の意思を上司に伝え、必要な手続きや引き継ぎを行うなど、ルールを守って退職することが、トラブルを避けるためには大切です。
ここでは、退職の意思を伝えるタイミングについて紹介します。
まず、自分の会社の就業規則を確認し、退職手続きがどうなっているのか調べましょう。一般的に、就業規則には「退職する場合は、退職予定日の30日前までに申し出ること」のように決められていることが多いです。
退職の申し出は、就業規則に則ったうえで、引き継ぎと有給消化の時間を十分に確保できるよう逆算し、1~3カ月前に伝えられるのが理想的です。
正社員など、あらかじめ契約期間が定められていない場合には、少なくとも2週間前までに退職願を提出することで、法律上はいつでも辞めることができます。
民法第627条第1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
(参照:e-Gov 法令検索「民法」)
つまり、退職を申し出てから2週間すれば、会社側の承諾がなくても、会社を辞めることができます。
ただし、円満退職のためには、先に述べたように就業規則を守り、引き継ぎなどの十分な期間を用意したほうがいいでしょう。
契約社員や派遣社員、アルバイトのように契約期間に定めのある有期雇用契約の場合は、契約期間の満了とともに労働契約が終了します。
原則として、契約期間中に辞めることはできません。ただし、勤続年数が1年以上の場合や、病気やけが、介護など、やむを得ない事情の場合は認められることがあります。
どうしても期間中に退職しなければならない場合は、上司に相談しましょう。会社とあなた双方の合意があれば、契約期間中でも合意退職することができます。
ここでは、退職するまでの一般的な流れと目安時期を紹介します。あなたの会社の就業規則を確認したり、上司に相談をしたりしながら、適切なタイミングで手続きを行いましょう。
手続き | 目安時期 |
|---|---|
1.就業規則の確認 | 退職を決めたらすぐ |
2.直属の上司へ退職意思を伝える | 就業規則で決められた時期(多くは約1~3ヶ月前) 遅くとも法律で定められた2週間前 |
3.退職願・退職届の提出 | 退職願:上司に退職意思を伝えるとき 退職届:上司と合意出来た後 |
4.引き継ぎ業務の準備 | 退職日の約1ヶ月~2週間前 |
5.社内外への退職挨拶 | 取引先:退職日の約1ヶ月~2週間前 社内:最終出勤日 |
6.有給の消化 | 退職日までに |
7.会社へ返却するものを返す | 最終出勤日 |
8.会社から必要なものを受け取る | 最終出勤日、または退職後 |

繰り返しになりますが、円満退職のためにはルールを守って退職することが大切です。
ただし、それ以外にも配慮することで円満に退職しやすくなるコツがいくつかあります。
ここでは、円満退職のためにおさえておいてほしいコツを紹介します。
退職することを最初に伝えるのは直属の上司です。他の人に先に伝えてしまい、上司が第三者から退職について聞かされる状況は好ましくありません。
伝える際には、ポジティブで前向きな退職理由を伝え、感謝の言葉も忘れないようにしましょう。
例文:
お忙しいところお時間をいただきありがとうございます。この度、自分が外でどれだけやっていけるのか、新しい環境で挑戦をしたいと考え、転職を決心しました。
これまでの、○○さんのご指導やサポートに心から感謝しております。
退職は○月末とさせていただきたいと考えています。現在担当しているプロジェクトについては、引き継ぎ計画を作成し、スムーズな移行ができるよう努めます。
ご迷惑をおかけしますが、退職について相談させて頂けますでしょうか?
退職の意思は口頭でも伝えられますが、退職願を渡すことで、退職の意志が固いことを示すことができ、あなたから会社へ退職を申し入れた書面での証拠にもなります。
自分が退職した後も、担当していた業務が滞りなく進められるように、仕事を引き継ぐことも円満退職のコツです。
退職時の引き継ぎは、上司に相談しながら、スケジュールを立てて計画的に行いましょう。
引き継ぎの際は、以下の3点を行うことをおすすめします。
自分の業務内容を詳細に記載したマニュアル。手順や注意点、使っているツールやシステムの説明などを残す。
後任の人と引き継ぎスケジュールを共有し、具体的な日程や内容を明確にしておく。
取引先に対して、新しい担当者を紹介する。メールや訪問で挨拶し、引き継ぎをスムーズに進めるためにサポートする。
基本的には有給休暇が残っている場合、退職前にすべて消化することが可能です。
しかし、有給休暇に入る前に、仕事の引き継ぎや最後の出勤日などをしっかりと計画することが大切です。
とつぜんあなたが抜けて、現場の混乱やトラブルにならないよう、スケジュールを会社や上司と話し合って、有給休暇の申請を行いましょう。
特に、まとめて消化する場合は職場や同僚にも配慮することが円満な退職のコツです。
ここでは、退職するときの注意点を紹介します。
退職の意思を伝えたときに、「考え直してくれないか」と引き止められてしまうケースも存在します。
まずは、なるべく引き止められないように、伝える際の以下のポイントを押さえておきましょう。
引き止める行為自体は違法ではありませんし、会社や上司が優秀な社員を手放したくないための自然な行動です。
ただし、引き止め方が不適切であったり、強制的なものであった場合は問題となります。
引き止めにあってしまった時は、「退職の意思は変わらない」ことをしっかり伝えることが大切です。
どうしても上司に退職願を受理してもらえないときは、さらに上の上司や人事部に直接提出します。
それでも受理されない場合は、内容証明郵便で退職願を送り、退職の意思を伝えた証拠を残します。
■ 退職時のトラブルで困ったら...
場合によっては、労基署(労働基準監督署)へ相談することも必要になるでしょう。
労基署は、労使間のトラブルも相談に乗ってくれます。
また労基署の他に、東京都のかた向けになりますが、東京都労働相談情報センターが都内5か所に設置されていて利用することができます。
基本的に、提出した退職届は撤回することができません。
退職届は「退職することが確定して、その退職日が決まった後」に会社に提出する書類です。
退職日を記載して提出した時点で退職日も確定してしまうため、退職日や本当に退職したいかをよく考えて決断しましょう。
転職先を決めてから退職したいと考える人も多いと思います。転職活動にかかる期間は人にもよりますが、おおよそ3カ月ほどです。
転職活動にかかる時間も考えて、いつ会社に退職を伝えるか、いつを退職日にするのか計画をたてましょう。
この記事では、退職することを何日前に伝えればよいのか、円満退職のためにはどうすべきかを紹介してきました。
退職の申し出は、法的には2週間前とされていますが、円満退職のためには、就業規則を守り、引き継ぎや有給消化の時間を考えて1~3ヶ月前に行うのが理想的です。
これまで一緒に働いてきた仲間に迷惑をかけず、快く送り出してもらえるよう、法律や会社のルールを守って退職を申し出ましょう。