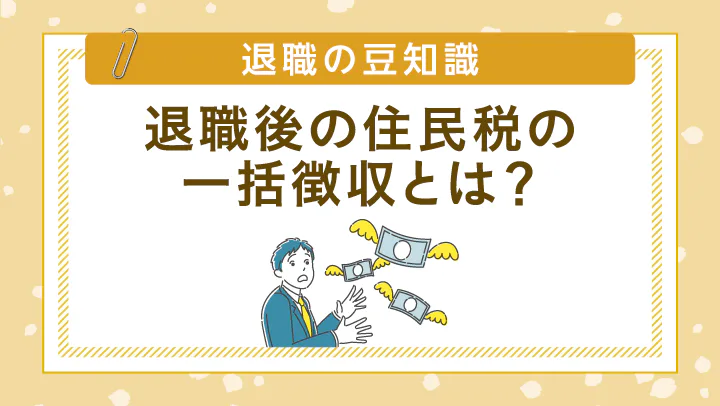
退職時に最終給与から引かれる住民税の「一括徴収」とは?【税理士監修】

仕事を辞めることを意識したとき、「何から始めればいいの?」「退職するために必要なことは?」と悩む人も多いのではないでしょうか。
退職の決断、上司への伝え方、退職後の手続きなど、退職にはさまざまなステップがあります。
この記事では、退職を考えている人に向けて、退職の準備から退職後の手続きまでを、わかりやすく解説します。
仕事を辞めることを考えたとき、本当に退職すべきなのか、今が退職するタイミングなのか悩みますよね。
ここでは、退職を決断する前におさえておいてほしいポイントを紹介します。
退職を考えたときにまず大事なのは、「なぜ仕事を辞めたいのか」という理由をしっかりと理解することです。
たとえば、仕事の内容に不満がある、職場の人間関係が良くない、もっとやりがいのある仕事がしたいなど、いろいろな理由があるでしょう。
それらを目に見えるよう書き出して、冷静に自分の気持ちを整理しましょう。
こうすることで、感情で決断するのではなく、落ち着いてどうするべきか考えることができます。
退職に踏み切る際は、自分にとってベストなタイミングで辞めることも大切です。
よく「最低でも3年間は同じ会社にいなさい」という意見も聞きますが、実際には3年未満で転職する人も多いです。
今の職場での成長が難しくなったり、新しいことに挑戦したくなったりしたときが転職のタイミングかもしれません。
また、職場でパワハラやいじめがある場合は、無理をせずに環境を変えるのも一つの手です。
結婚や子育て、住宅ローンなどのライフイベントも考慮に入れて、退職のタイミングを見つけましょう。
仕事を辞めることは労働者の自由ですが、何も告げずに、とつぜん会社に行かなくなるのはルール違反です。
まずは、退職の意思を伝え、必要な手続きや引き継ぎをしっかり行うことが、トラブルを避けるためには大切です。
ここでは、退職するまでの流れや手続きを紹介します。
全体像を把握して、退職までの自分のスケジュールを考えましょう。
■ 退職を決めてから最終出勤日までの10ステップ
_01.png)
ここでは、退職を決心してから、退職日までにやるべきことを紹介します。
多くの場合就業規則に、退職手続きのルールが書かれており、たとえば退職を申し出るタイミングや、退職届の提出方法などが決められています。
そのため、退職を決めたら、まずは自分の会社の就業規則を確認しましょう。
はじめに退職に関するルールを把握しておくことで、スムーズに準備を進められます。
退職の意思を伝える際には、1~3カ月前に上司に報告するのが理想的です。
これだけの期間があれば、会社も後任者の準備ができ、あなたも仕事の引き継ぎや有給休暇の消化を十分に進められます。
ただし、法的には2週間前に申し出ることで退職することが可能です。
また、退職の意思は口頭で伝えるだけでなく、退職願を提出し、書面で残すことで、退職の意志が固いことや、あなたから会社へ退職を申し入れた証拠になります。
一般的に退職するのに良いと言われているのは、以下のような時期です。
退職後に経済的に困らないためにも、ボーナスをもらってからや、転職先を決めてから退職をするのがよいでしょう。
また、退職によって現職の職場に迷惑がかかりにくい時期を選ぶのも、円満退職を目指すうえでは大切になります。
退職届は、退職の決定を正式に会社へ伝えるための書類です。退職届には、退職理由や上司と合意した退職日を記載します。
これを提出することで、「この日に退職します」と会社に通知できます。
退職届を提出すると、その後に撤回することは基本的にできないため、提出前にしっかりと考え、準備をしてから提出することが大切です。
退職する際には、自分が退職した後も、担当していた業務が滞りなく進められるように、仕事を引き継ぐことが求められます。
引き継ぎは、引き継ぎ資料を作成し、スケジュールを立てて計画的に行いましょう。
また、引き継ぎと平行して取引先など社外の関係者へ挨拶を行います。
退職することを報告し、これまでの取引に対する感謝の気持ちと、後任へ責任を持って引き継ぐことを伝えなければいけません。
可能であれば、挨拶の際に後任者と一緒に訪問して紹介すると、よりスムーズに引き継ぎを行えます。
退職を決めたら、有給休暇がどのくらい残っているか確認しましょう。
もし残っている場合は、退職前にすべて消化するように計画をたてます。仕事の引き継ぎや最後の出勤日などを含めて、上司と相談しながら計画することが大切です。
特に、まとめて休暇を取りたい場合は、早めに希望を伝え、職場や同僚にも配慮することが円満退職のためのポイントになります。
最終出社日が来たら、会社を後にするための最後の準備を行います。
ここでは、最終出社日にやるべきことを紹介します。
最終出社日にまず行うべきことは、引き継ぎの最終確認です。
引き継ぐべき資料がすべてそろっているか、後任者に必要な情報がしっかりと伝わっているかをチェックしましょう。
万が一、伝え忘れていることがあれば、このタイミングで補足する必要があります。
社内の人への挨拶は、最終出勤日に最後の挨拶として行うことが一般的です。
退職理由や転職先を詳しく話す必要はありませんが、これまでお世話になったことへの感謝の気持ちを伝えることが大切です。
挨拶のタイミングは、業務の邪魔にならないように、忙しくない時間を選びましょう。
退職時には、会社から借りていたものを全て返却しなければいけません。
これらは会社の財産なので、そのまま持ち帰らないように必ず最終出社日までに返しましょう。
【主に返却するもの】
□ 健康保険証
□ 社員証
□ 制服
□ 会社の備品(パソコン、携帯電話など)
□ 名刺(自分のものと、取引先のもの)
退職時には、会社から退職後の手続きや転職先で必要になる書類を受け取ります。
書類によっては、退職後に郵送で受け取ることもあります。
【主に受け取る書類】
□ 離職票(雇用保険の申請に必要)
□ 健康保険資格喪失証明書(新しい健康保険への切り替えに必要)
□ 年金手帳(年金の手続きに必要)
□ 源泉徴収票(確定申告や転職先の年末調整に必要)
□ 退職証明書(転職先への提出に必要)
□ 雇用保険被保険者証(会社で年金手帳と一緒に保管している場合が多い)
中には、退職の当日ではなく、後日郵送で送られるものもあるので、その点も確認しておくと安心です。

ここでは、退職した後に必要になる手続きについて紹介します。
期間を空けずに次の企業に就職する人は、転職先の会社が手続きをしてくれるため、比較的シンプルです。
健康保険や年金の手続きを、あなた自身で行う必要はほとんどありません。
また、税金も給与から天引きされるため、特別な手続きは不要です。
転職先から指示された書類を提出するだけで大丈夫です。
終業先で社会保険に加入したり、税金を天引きしてもらえなくなる人は、自分で下記の手続きをする必要があります。
これに当てはまるのは、退職してから就職活動をする人、家族の扶養に入る人、自営業やフリーランスとして働く人などです。
ここでは、自分でやらなければならない手続きの概要を説明します。
手続きの詳しい内容は、以下の関連記事で詳しく紹介しています。
また、失業状態にある人は、雇用保険の基本手当(※一般的に失業手当、失業保険と呼ばれるもの)の申請をすることができます。
失業状態とは、就職しようとする積極的な意思と能力があるにもかかわらず、自分の努力やハローワークのサポートを受けても、なかなか仕事が見つからない状態です。
こちらは「失業期間のある人は受けられるサポートを確認」で紹介します。
転職先の保険に入らない場合は、健康保険を切り替える必要があります。
選択肢は以下の3つです。
・健康保険任意継続
会社を退職した後も任意で、退職した会社の健康保険を続けることができる制度です。
退職日までに2ヶ月以上、健康保険に加入していることが加入の条件です。
・国民健康保険
住民票のある市区町村の役所で、退職後14日以内に手続きが必要です。
・家族の健康保険(被扶養者)
家族が勤務する企業・団体で保険に加入している場合、その保険に被扶養者として加入できます。手続きは、退職後すぐに、扶養する家族が行います。
ただし、被扶養者になるには収入や就業状況などの条件を満たさなければいけません。
退職すると、これまで加入していた厚生年金から自動的に離脱してしまいます。
すぐに転職先企業に就職しない場合には、年金の切り替え手続きが必要です。
選択肢は以下の2つです。
・国民年金
住民票のある市区町村の役所で、退職後14日以内に手続きが必要です。
国民年金は、20歳以上60歳未満まで加入することになっています。このため60歳未満であれば手続きを行わなければなりません。
・配偶者の扶養に入る
退職後の1年間の収入が130万円未満と見込まれる場合に限り、配偶者の扶養に入ることができます。
この場合は、自身で国民年金保険料を支払う必要はありません。
転職先で給料から天引きしてもらえない場合は、自分で納付します。
しかし、住民税は退職の時期により、支払い方法が変わります。
・1月1日~5月31日に退職(1か月以上離職期間がある)
1月1日~5月31日までに退職する場合は、最後の給料で残りの住民税をまとめて天引きすることができるので、自分で納付する必要はありません。
手続きが簡単な一方、手取り額が大幅に少なくなるおそれがあります。
・6月1日~12月31日に退職(1か月以上離職期間がある)
6月1日~12月31日に退職をする場合は、退職する会社で残りの住民税を一括で天引きしてもらうか、3か月に1度分割で支払う「普通徴収」に切り替えるか選びます。
自分で納付するのが面倒な人は、退職する会社にて一括で天引きしてもらう方法がおすすめです。
退職する前に、前もって会社に手続きについて相談・依頼しましょう。
普通徴収に切り替える人は、特に手続きを行わずに退職をすれば、自動で切り替わります。
所得税は、個人の所得に対してかかる税金です。
会社員の場合は、会社が年間の給与額を予測して毎月の給与から天引きし、12月に年末調整をおこなって過不足を計算し、対応してくれています。
すぐに次の会社に就職せず、下記の3つに当てはまる場合には、退職した年の翌年の3月15日までに税務署で「確定申告」を行う必要があります。
※確定申告とは
確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得金額とそれに対する税金を計算し、期限までに確定申告書を提出します。これにより、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金の過不足を精算します。
退職後の生活をスムーズに進めるためには、事前にしっかり計画を立てて退職することが大切です。
ここでは、主に転職について紹介します。
転職のために退職する場合は、転職先を決めてから会社を辞めることをおすすめします。
転職先を決めずに退職をしてしまうと、思うように転職活動が進まなくなったときに、精神的にも経済的にも余裕がなくなり、転職活動に集中できなくなってしまうかもしれません。
また、転職先が決まっていれば、退職日も転職先の入社日に合わせて調整し、決めやすくなります。
雇用保険では、失業状態の人が早く再就職できるように、さまざまなサポートが用意されています。
一般的に失業手当や失業保険と呼ばれる、雇用保険の基本手当は、失業期間中に就職活動に集中するため、生活を安定させる目的で支給されます。
再就職するまでの期間の手当を希望する人は、会社から「離職票」を受け取ったらハローワークで申請を行いましょう。
退職の理由が、会社都合か自己都合かで受給内容が変わるので要注意です。
また、ハローワークでは就職を目指す人向けに、個別相談や職業訓練、セミナーといったサポートも提供しています。
(参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」、厚生労働省「ハローワークの相談支援」)

退職を円満に進めるためには、正しい手続きと周囲への配慮が必要です。
ここでは、トラブルを避けてスムーズに退職を進めるためのポイントを紹介します。
退職時には、会社の就業規則を守ることが大切です。
たとえば、退職の申し出は法律では最低でも2週間前までとされていますが、就業規則では1カ月前やそれ以上の期間を求められることが多いです。
極端に就業規則の期間が長いなど、特別な事情がない限りは、就業規則にある退職ルールを守りましょう。
ルールを守って退職手続きをすることで、トラブルを避け、円満退職しやすくなります。
退職する際には、職場の同僚や上司に迷惑をかけないような配慮が大切です。
退職後に業務が滞らないような引き継ぎを心がけたり、有給休暇を無理のないスケジュールで取得したり、挨拶を忙しくない時間にしたりなど。
あなたの退職でできるだけ職場に迷惑がかからない工夫をしましょう。
退職をスムーズに進めるためには、退職の全体像を把握したうえで、計画的に進めることが大切です。
退職後までの一連のスケジュールを具体的に立て、必要な手続きや書類を確認しておきましょう。
退職を意識し始めたら、自分の考えや気持ちを整理し、退職したい理由を明確にしましょう。
そして、今が自分にとって退職するベストなタイミングなのかも冷静に判断しなければなりません。
退職を決心したら、退職するまでの流れとやるべきこと、退職後に必要になる手続きをチェックします。
退職の全体像を理解して行動することで、スムーズに退職をすることができます。
感謝の気持ちを忘れずに職場との関係を大切にすることが、円満退職のポイントです。
周囲に迷惑をかけないよう、計画的に退職に向けて動きはじめましょう。