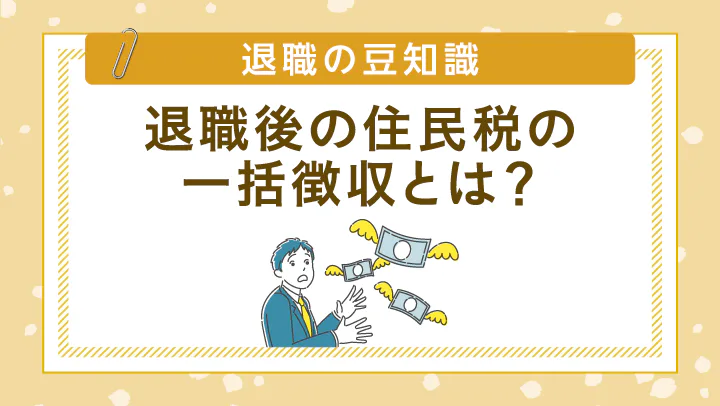
退職時に最終給与から引かれる住民税の「一括徴収」とは?【税理士監修】
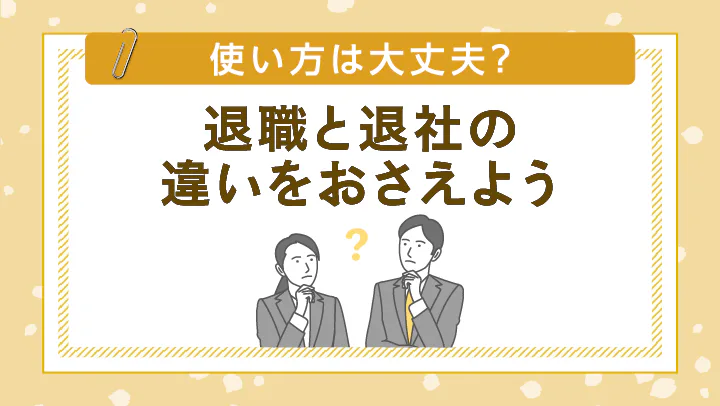
「退職」と「退社」という言葉の違いを正しく説明できますか?
どちらも会社を辞めるという意味を持つ言葉ですが、履歴書や面接、ビジネスシーンでどちらを使うべきか困ったことのある人も多いのではないでしょうか。
この記事では、「退職」と「退社」の違いと、さまざまなシチュエーションでの使分けについて解説していきます。
ここでは「退職」と「退社」という言葉の違いを解説します。
言葉の使い分けを理解し、就職・転職活動やビジネスシーンで正しく使いましょう。
「退職」とは、会社を辞めることを意味します。一時的に休む「休職」とは違い、会社との雇用契約を終わらせることを指します。
退職する場合には、正しい手続きを踏み、労働者が自分の意思で辞めることになります。
退職の使用例:
「一身上の都合により退職いたします」
「来年、定年退職をする予定です」
一方、「退社」は会社を去ることを意味しますが、二つの使い方があります。一つは「会社を辞める」という意味で、もう一つは「その日の業務を終えて会社を出る」という意味です。
このため、「退職」とは違い、日常の業務終了後に会社を出る場合にも「退社」という言葉を使います。
退社の使用例:
「今日は退社後に、友人と食事に行く予定です」
「○○は先月末で退社しております」
就職や転職活動をする際、求人に応募するために欠かせないのが履歴書です。
履歴書には一般的な書き方やマナーがあり、多くの人が悩むのが、職歴欄に「退職」と「退社」のどちらを使うべきかです。
ここでは、履歴書の職歴欄ではどちらを使うべきかについて説明します。
「退社」も「退職」も、どちらも会社を辞めたことを表す言葉です。
そのため、履歴書にはどちらを書いても間違いではありません。
しかし、複数の意味をもたない「退職」を使ったほうが、より正確に意味が伝わるでしょう。
また、「退職」という言葉は、会社だけでなく、病院や役所、学校など「会社ではない職場」を辞めるときにも使えます。
そのため、履歴書では「退職」を使用するのが一般的です。
履歴書の職歴欄では、具体的な退職理由まで書かないことが一般的です。具体的な退職理由や経歴の補足は、職務経歴書で行います。
退職までの期間が短かったり、転職回数が多かったりすると、「会社をすぐにやめてしまう人なのではないか」と採用担当者が不安に思うかもしれません。
そのため、退職した理由を説明することで、不安を払しょくし、納得してもらいやすくなるでしょう。
履歴書で「退職」を使用するので、他の応募書類でも統一して「退職」を使用すると、一貫性を保つことができます。
■履歴書の職歴欄の記入例

たとえば、自己都合で会社を辞めた場合や、会社の都合で退職した場合、または在職中に辞める場合など、さまざまなケースで「退職」を使用します。
アルバイトやパート、派遣社員の場合も「退職」を使うことが適切です。
具体的な使い方については、以下の表を参考にしてください。
ケース | 記入例 |
|---|---|
自己都合で辞めた | 一身上の都合により退職 |
会社都合で辞めた | 会社の都合により退職 |
退職日が決まっていて在職中 | 現在にいたる(○月○日退職予定) |
アルバイトを辞めた時 | 一身上の都合により退職 / 契約期間満了により退職 |
パートを辞めた | 一身上の都合により退職 / 契約期間満了により退職 |
派遣社員を辞めた | 派遣期間満了につき退職 |

面接では、言葉の使い方がとても大切です。正しい言葉を使うことで、面接官との間に誤解を生むことを避けることができます。
ここでは、面接での「退職」と「退社」の使い分けについて、例を用いて説明します。
履歴書とおなじく、どちらを使用しても間違いではありませんし、選考結果にも響くことはありません。
ただし、面接官は応募書類を見ながら、面接をすることも多いので、履歴書とあわせて「退職」を使うことをおすすめします。
また、会社を辞めることのみを意味する「退職」を使った方が誤解が少なく、正確に伝えられるでしょう。
特に転職の面接では、「退職理由」を聞かれることがよくあります。
答える際には、きちんと「退職」「退社」を使い分けられるように注意しましょう。
例文:
私は、自己成長のために、新しい環境に身を置きたいと考え、退職を決意しました。
現職では多くの業務を経験し、さまざまなスキルを身につけることができました。しかし、残業が常態化しており、退社が最終電車に間に合わないことも珍しくありません。そのため、自己啓発や新しい技術の勉強に時間を割くことが難しい状況です。
より効率的な働き方や人員の増強を何度も提案してきましたが、環境を改善するには至りませんでした。そのため、この現状を変えたいと思い転職活動を始めました。
日常のビジネスシーンでも、正しい言葉を使えているか不安になることがあるのではないでしょうか。
特に正しい表現が出来ているか心配になるのが、取引先や上司との会話ですよね。
ここではビジネスシーンでの「退職」と「退社」の使い分けだけでなく、その他の紛らわしい言葉についても説明します。
まずは、「退職」と「退社」と紛らわしい、「退勤」や「離職」、「辞職」などの言葉について紹介します。
退勤は、「仕事(業務)を終える」という意味です。「退社」と似たような意味ですが、厳密には少し違いがあります。
たとえば、「午後からテレワークをするため、12時に退社して、自宅で18時まで業務を行い退勤した」のように、仕事(業務)を終えたタイミングと、会社(オフィス)を出たタイミングで使い分けすることができます。
離職は、仕事を辞めることを意味しますが、仕事から離れている状態を指すときにも使います。
たとえば、会社を辞めた後、新たな仕事に就くまでを「離職中」や「離職期間」と言います。
辞職は、自分の意思で仕事を辞めることを指します。特に、役員や管理職のような高い地位の人が使うことが多いです。
一般の社員はあまり使いません。
似た意味を持つ言葉がたくさんありますが、正しく使い分けることが大切です。
さらに、言葉を補うことで誤解を避けることができます。
例えば、「退社」という言葉を使うときには「本日○○はすでに退社いたしました」や「明日は9時に出社の予定です」といった言葉を添えます。
これにより、会社を辞めたのではなく、会社から出たのだと、具体的な状況が相手に伝わりやすくなります。
ビジネスシーンでの例:
「○○は一身上の都合により、来月末で退職することとなりました」
「本日はすでに退社してしまいましたので、ご用件は明日9時以降に対応いたします」
「今日は6時に退勤予定です」
「現在は、転職活動をおこなっており、離職中です」
「昨日役員の○○さんが辞職を表明しました」
どちらを使うべきか悩んでしまう「退職」と「退職」には、どちらも会社を辞めるという意味があります。
しかし、退社には他にも、「その日の業務を終えて会社を出る」という意味でも使われるという違いがあります。
また、「退職」という言葉は、会社だけでなく、病院や役所、学校など「会社ではない職場」を辞めるときにも使えます。
そのため履歴書や面接の場面では「退職」を使うようにしましょう。
ビジネスシーンでは、誤解を招くことなく、伝えたいことを正確に伝えるためにも、言葉の違いを正しく理解して使い分けられることがベスト。
相手の分かりやすさを考えて、伝え方を工夫することを常に心がけましょう。